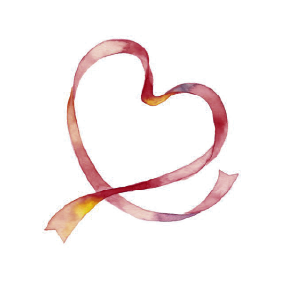障害ナースの語り
慢性疾患や障害のある人が病気やケガで医療機関にかかるとき、そこに同じように病いや障害を経験した医療従事者がいることはとても心強いことです。近年、そうした医療従事者の多様性が重要視されるようになっており、現に様々な病いや障害を持つ看護学生が看護を学び、看護職として活躍しています。
障害ナースの語りでは、病いや障害をもちながら看護を学んでいる方や、看護職として働いている20代から70代の20名にインタビューをした内容を掲載しています。そのうち7名は、「障害学生の語り」プロジェクトの際にインタビューをした看護専攻の方々です。
■「障害ナース」という名前について■
日本語では、本人の内側にある心身の機能障害(英語のインペアメント/impairment)と、社会が多数派向けに作られていることで少数派の心身を持つ人が困る状況を表す社会の側の障害(ディサビリティ/disability)が、同じ「障害」という言葉で表されます。
障害がどこにあるのか?という問いに対して、人の内側にあると考えるのは「障害の医学モデル(個人モデル)」で、社会にあると考えるのが「障害の社会モデル」と呼ばれてきました。現代では、障害は「障害の社会モデル」で考える必要があり、社会側の調整が必要という考え方になっています。
今回の「障害ナース(の語り)」の「障害」は後者で、「多数派向けにできている社会に対して困りごと(障害)を感じている看護職/看護学生の方々」(の語り)という思いを込めて名付けました。変わる必要があるのは、多数派向けに作られている社会の側だと感じています。
またご自身の置かれた状況をどのように捉えるかは、人それぞれです。医学的に機能障害があっても「自分のは障害ではなく個性」と捉える人もいますし、疾患と障害は区別したいと話された方もいます。「障害ナース」という言葉だけでは全体を表わせないですが、多様な方がおられることを、ぜひ1人1人の語りから感じて頂けたらと思います。
各テーマのページを開くと、そのテーマについて語っている体験者たちの 1-4 分の短い「語り」の映像・音声・テキストを見ることができます。
また、年代別・障害区分別のページから、 個々の体験者の語りを見ることもできます。それぞれのページに入るには、 各タイトルをクリックしてください。(2025年3月公開)
※今後順次テーマを追加公開していきます。
語ってくれた人たち
語りの概要
インタビュー期間
2021 年 12 月 ~ 2022 年 6 月
(「障害学生の語り」のインタビューは、2018 年 12 月 ~ 2021 年 8 月)
対象者
障害ナースの語り:20 代から 70 代の本人 20 名
「障害ナースの語り」データベースの作成は、文部科学省科学研究費(JSPS科研費JP 19K19513:研究テーマ名「障害や病いを持ちながら就業もしくは修学する看護職/看護学生による体験知の蓄積」研究代表者・瀬戸山陽子)の助成を受けて作成されました。
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。