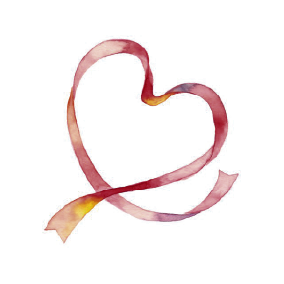インタビュー時:62歳(2012年9月)
関係:長女(実父母を介護)
診断時:父81歳、母80歳で診断されたのは長女52~54歳の頃
2002年に2世帯同居の実父が脳血管性認知症の診断を受け、2年後にレビー小体型認知症と判明。同じ頃、実母もアルツハイマー型認知症の診断を受けて、しばらくひとりで2人の介護をしていたが、父の脳梗塞をきっかけに母は有料老人ホームに入所。2006年秋、父は肺炎で入院中し、そのまま帰らぬ人となった。その後、母に腎臓がんが見つかったが、本人の意思もあって手術はせず、2011年秋に自宅に引き取り、亡くなるまでの3カ月間、在宅で看取った。
プロフィール詳細
M.W.さんは、首都圏に暮らす夫と2人の子どもを持つ専業主婦。介護が始まるまでは日本語教師のボランティアをしていた。2002年、2世帯同居で階下に暮らしていた実父が、夜中に家を出ていこうとしたり、幻視が見えたりするようになり、大きな病院の神経内科を受診、脳血管性の認知症(当時は「痴呆」と呼ばれていた)と診断された。幻視を抑える薬として処方されたグラマリールで、口からよだれを流して横になったきり自分では起き上がれないよう(パーキンソン症状)になってしまったので、服薬中止。その後パーキンソン症状に対して出された薬も合わなかったため中止。それから約2年間、かつて建築関係の仕事をしていた父が、現場に行こうとして夜中に出ていくのを止めたり連れ戻したり、ということを毎晩のように繰り返していたところ、ケアマネジャーに地元の開業医を紹介され、受診してレビー小体型認知症(当時はレビー小体病)と診断された。そこで初めて「こういうところに気を付けて生活したらいいですよ」というアドバイスを得ることができ、父も自分の状態を理解してもらえてとても喜んでいた。
骨折を繰り返していた母の介護もあるため、父には昼間デイサービスに行ってもらうことにした。初めは嫌がっていたが、後に移った小規模な施設が肌に合ったのか落ちつきを取り戻し、次第に夜の徘徊も収まった。しかし、同じ頃母が脳梗塞を起こし、その後娘の名前を言い間違えるようになったため、検査を受けたところ、かなり進んでいるアルツハイマー型認知症と診断された。ヘルパーの助けを得ながら、何とか2人の介護を続けたが、要求の強い母と夜間せん妄状態の父の両方の夜間介護はとにかく大変だった。ひとりで抱え込んで介護を続けるうち、体力も限界がきて、母を叩いてしまった。医師に相談したところ、「これはもう黄色信号ではなく赤信号だ」と言われ、母の施設入居を勧められた。非常に葛藤したが、今度は父が脳梗塞を起こして身体機能が落ちてきたため、個別的なケアを必要とする父を在宅で介護することにして、母には有料老人ホームに入ってもらった。
父は次第に嚥下機能が悪くなったため、本人とも相談の上胃ろうを付けることになったが、半年ほどして肺炎を起こし、2006年11月、病院で亡くなった。亡くなる直前まで、きちんとコミュニケーションが取れ、前向きに生きようとしていた。
一方、ホームに入った母は月1回、3~4日家に戻ってきていて、初めのうちはホームに戻るのを嫌がったが、次第にホームのことを「うち」と呼ぶほどに馴染んでいった。しかし、2009年になって下血があり、腎臓がんが見つかった。母は若い頃は看護師をしていたこともあり、本人に手術をするかどうか聞いたところ、一日考えた上で「手術はしない」と答えた。積極的な治療はせずそのままホームで様子を見ていたが、2011年秋に食欲が落ちてきたということでホームから連絡があり、最期を看取るため自宅に引き取った。在宅ホスピスケアを受け、モルヒネで痛みを緩和しながら、静かに見送ることができた。自宅に戻ってからは父の時と同じように、昔の母に戻って普通にコミュニケーションができるようになっていたのが、不思議だった。
振り返ってみて、最初の医師との出会いで幸せな道と不幸な道が2つに分かれてしまうのはおかしいと思う。2カ月に1回検査をして「はい、じゃあまた、普通に暮らして下さい」では、認知症の人の生活を支えていくことはできない。特にレビー小体型認知症については、薬剤過敏があることを医師もよく知らなかったり、施設でも他の認知症とは対応の仕方が異なることを分かっていなかったりして、介護する家族の苦労は大きい。周囲が病気についてしっかり勉強して、症状を知ってさえいれば、介護、介護と言わなくても、自然な形で生活できるのではないかと思う。父が亡くなってから始めたレビー小体認知症の家族の集まりへの参加を通じて、家族だけでなく医療者の意識改革をめざして頑張っている。
*せん妄状態とは、意識がはっきりしていない上に幻覚や錯覚が見られる状態です。
骨折を繰り返していた母の介護もあるため、父には昼間デイサービスに行ってもらうことにした。初めは嫌がっていたが、後に移った小規模な施設が肌に合ったのか落ちつきを取り戻し、次第に夜の徘徊も収まった。しかし、同じ頃母が脳梗塞を起こし、その後娘の名前を言い間違えるようになったため、検査を受けたところ、かなり進んでいるアルツハイマー型認知症と診断された。ヘルパーの助けを得ながら、何とか2人の介護を続けたが、要求の強い母と夜間せん妄状態の父の両方の夜間介護はとにかく大変だった。ひとりで抱え込んで介護を続けるうち、体力も限界がきて、母を叩いてしまった。医師に相談したところ、「これはもう黄色信号ではなく赤信号だ」と言われ、母の施設入居を勧められた。非常に葛藤したが、今度は父が脳梗塞を起こして身体機能が落ちてきたため、個別的なケアを必要とする父を在宅で介護することにして、母には有料老人ホームに入ってもらった。
父は次第に嚥下機能が悪くなったため、本人とも相談の上胃ろうを付けることになったが、半年ほどして肺炎を起こし、2006年11月、病院で亡くなった。亡くなる直前まで、きちんとコミュニケーションが取れ、前向きに生きようとしていた。
一方、ホームに入った母は月1回、3~4日家に戻ってきていて、初めのうちはホームに戻るのを嫌がったが、次第にホームのことを「うち」と呼ぶほどに馴染んでいった。しかし、2009年になって下血があり、腎臓がんが見つかった。母は若い頃は看護師をしていたこともあり、本人に手術をするかどうか聞いたところ、一日考えた上で「手術はしない」と答えた。積極的な治療はせずそのままホームで様子を見ていたが、2011年秋に食欲が落ちてきたということでホームから連絡があり、最期を看取るため自宅に引き取った。在宅ホスピスケアを受け、モルヒネで痛みを緩和しながら、静かに見送ることができた。自宅に戻ってからは父の時と同じように、昔の母に戻って普通にコミュニケーションができるようになっていたのが、不思議だった。
振り返ってみて、最初の医師との出会いで幸せな道と不幸な道が2つに分かれてしまうのはおかしいと思う。2カ月に1回検査をして「はい、じゃあまた、普通に暮らして下さい」では、認知症の人の生活を支えていくことはできない。特にレビー小体型認知症については、薬剤過敏があることを医師もよく知らなかったり、施設でも他の認知症とは対応の仕方が異なることを分かっていなかったりして、介護する家族の苦労は大きい。周囲が病気についてしっかり勉強して、症状を知ってさえいれば、介護、介護と言わなくても、自然な形で生活できるのではないかと思う。父が亡くなってから始めたレビー小体認知症の家族の集まりへの参加を通じて、家族だけでなく医療者の意識改革をめざして頑張っている。
*せん妄状態とは、意識がはっきりしていない上に幻覚や錯覚が見られる状態です。
インタビュー家族34体験談一覧
- 父が真夜中に外に出ていくことが何度か続いておかしいとは思ったが、記憶力や判断力に何の問題もなかったので、認知症になるとは思ってもいなかった
- 父が脳血管性認知症という診断で2年間通った病院では5分診療で空しく感じていた。ケアマネージャー(ケアマネ)に紹介された開業医に行ってみたら、レビー小体型だとすぐにわかった
- レビー小体型認知症に抗認知症薬は劇的に効くが、次第に副作用が出て、飲み続けられなくなることが多い。家族会では薬の分量を微調節して穏やかな日々が送れているという話を聞く
- 幻視を抑えるために出されたグラマリールを飲んだ途端に動けなくなり、口からよだれを垂らして廃人のようになった。ネットで調べたら同様の症状の人がいた
- レビー小体型認知症にはアリセプトがよく効くが、パーキンソン症状を抑えるための薬も飲む必要があり、そのバランスが難しい。父は薬剤過敏だったので、ほとんど薬は飲めなかった
- レビー小体型認知症の父は最後まで理解力があって「自己」がしっかりしていたが、アルツハイマー型認知症の母は「本来の母」が消えてしまったようだった
- 父が「会社の部下たちが来ている」と言って、誰もいない部屋でテレビに向かって椅子を人数分並べてニコニコしていたのを見て、息が止まりそうになった
- 解剖してみなければ本当の病名はわからない中で、医師は診断名をつけている。それでも特定のタイプに特化した家族会があるのは病気によってケアの仕方が違うから
- 失禁で汚れてしまったシーツと布団を、父が浴槽に入れていたのを見つけてイライラしたが、あとから思うと父は父なりに解決しようとしてやったことなのだろう
- 夜中に階下で物音がして見に行くと、レビー小体型認知症の父が、アルツハイマー型認知症の母を車いすに乗せ、真っ暗な室内をぐるぐる回っていて、どうしたらいいかわからなかった
- 介護の言葉では「徘徊」というが、父が夜中に出かけていくのには、せん妄状態(※)で見えている家の前の行列について警察に相談しに行くといった、はっきりした理由がある
- レビー小体型認知症の父はせん妄状態で元気よく歩きだすが、我に返った瞬間に脱力してドサッと倒れてしまうので、誰かがついていないと危ない
- 父の徘徊はデイサービスに行くようになったら突然治まった。おそらくその場に家では見つからない自分の存在価値を見出せたのではないか
- レビー小体型認知症の人は、いきなり後ろから声をかけられると驚いて抵抗することがある。それが施設では「不穏」とされてしまうが、正しい対応をすれば問題はないはずだ
- 父がある日突然、娘である自分に向かって「あなたは副社長だ」「娘は嫁に行ったはずだ」と言い出した。20分ほどの出来事だったが、私がショックで寝込んでしまった
- 父のお気に入りの椅子に誰かが座っていて気持ち悪いからどうにかしてくれ、といわれたので、塩を置いてお浄めをすると翌朝「現れなかった、よかった」と言っていた
- 脳梗塞のあとは父の幻視やせん妄も規模が小さく可愛くなって、自分も慣れて来たので父と一緒に幻視を楽しめるようになった
- 両親2人の介護に限界を感じていたとき、主治医から、レビー小体型の父のほうが繊細なケアが必要だから母を施設に預けるように言われた。決断して踏み出すまでが勇気が要った
- 母は施設に入れられることを嫌がり「鬼娘」とののしったが、また帰ってこられるからと言ったら納得して行ってくれた。ホームでケアを受けるようになると落ち着いて、穏やかになった
- 親子3人でタッグを組んで頑張ろうと認知症の両親の介護にのめり込んだ。夫や子どもたちは両親の変化を自然に受けとめ、きりきりしていた私とバランスが取れていたと思う
- レビー小体型認知症の家族会のニューズレターでは、今後は積極的に医師に働きかけていくことにした。家族目線で医者の気持ちを引っ張り出したい
- 仲のいい夫婦で父を尊敬していた母は、父のことを「ぼけちゃった」と悔しがっていた。亡くなってからわかったが、母なりに認知症を勉強し、いろいろ考えていたようだ
- 父がレビー小体型認知症だと診断され、医師に気をつけることを教えてもらい、2年間のもやもやが晴れて在宅介護を続けることができた。父も原因がわかって嬉しかったと思う
- 失神して救急搬送された際に胃ろうにするかどうかの選択を迫られた。主治医の助言で父の意思を確認したら、まだ頑張りたいから胃ろうをつけると言った
- 母に腎臓がんがみつかり、手術をするかどうか悩んだ。本人に聞いてみたらその日はクリアで「一日考えさせてくれ」といい、翌日も覚えていて手術はしないとはっきり言った
- 肺炎になってしまい、父も病院に行こうというので、連れていったらそのまま入院となり1カ月後に亡くなった。最後まで治そうと頑張った姿はこれまでの父の生き方が出ていた