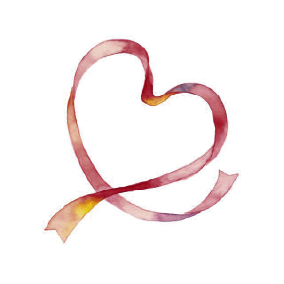※写真をクリックすると、動画の再生が始まります。
インタビュー時:43歳(2020年8月)
関係:母
医療的ケアのある子:三男5歳
首都圏在住。夫と、長男・次男(双子14歳)、三男、長女(生後5か月)の6人家族。
2015年帝王切開で出産した三男は出生直後から呼吸がなく、集中治療が必要となり、生後3か月で難治性てんかんの一種の大田原症候群と診断された。医療的ケアは気管切開、人工呼吸器(自発呼吸をサポート)、気管内吸引、口腔・鼻腔内吸引、胃ろう。てんかん治療のためケトン食療法を取り入れている。
訪問看護、ショートステイなどを利用。三男出産をきっかけに退職後、自宅で起業。
語りの内容
なぜ引っ越しをしたかですが、当時住んでいたのが一軒家で、主人のお父さんお母さんと同居をしていたので、われわれの居住スペースは、常に2階3階で、呼吸器の子を連れて帰るということは、外出のたびに階段で上り下りをしなければいけない。
マンションに引っ越さないと危ないというのが、大きな一つの決め手でした。
あとは同居する祖父母がおりますので、毎日訪問看護さんが来る、ヘルパーさんが来るという状況に巻き込むのも難しいことが予想されましたので、思い切って、ここは引っ越しをしてというふうに入院中に、考えまして。
周りのママたちもみんな引っ越してます。お風呂に入れられないとか、近所の人たちの知らないところに引っ越したいとか、いろいろママたちの背景はあるんですけれども、ほとんどの方が引っ越しをされていて。
引っ越し先を見つけるフェーズに入ったときに、活躍してくださったのが、病院の在宅支援室のナースの方ですね。
その方が、一覧にしてペライチ(一枚紙)の資料を持ってきてくださったんですね。
高層マンションに住むときは何階まで。高さですね。
何しろ高層マンションの場合、高ければ高いほどエレベーターが来ないので、救急隊員の到着が遅れて、命を大きく左右するので、なるべく地面に近いところに住みなさいという(笑)、ガイドライン。
あとは救急車ですね。
救急車が通れる道幅2メートルはないと駄目、そこに救急車が横付けできるスペースがないと駄目という道幅であったり。
それから住んでる地域ですね。
23区内にしなさい。
医療保険の自己負担金に差が出るので、できれば23区内で探しなさい。
いろんな要件をまとめたペライチをくださったんですね。で、そこの中の点をつくような全てを満たす物件を(笑)探しまして、現在の住まいに落ち着きました(笑)。
――おうちを探すときのその家の中の条件って、どういうことがあったんですか。
廊下が少なくバリアフリーであること。
将来この子が家の中をバギーで移動したり、リフトとかあるとは思うんで、その点を想像すると、まず家の中に段差があってはいけない。
できる限り廊下は少ないほうがよい。90度に曲がることができないので、そういう点を注意して探したり、お風呂に入れられるスペースを確保するために、脱衣所であったり、お風呂が大きいおうちというのを探しました。
インタビュー06体験談一覧
- 兄達が小学校の友達に「俺の弟かわいいだろ」と紹介していて、これでいいんだと自己肯定感が高まった
- 退院前に夫と小3だった双子の兄も2日間の研修を受けた。三男を在宅で受け入れる気持ちが家族内でぐっと高まった
- 三男の退院時に、三男の命ファーストという家の憲法を決めた。家族全員の役割が自然と決まり、家族全体を成長させてくれた
- 家でPC作業などを受けていたが、家にあるピアノを使って、先生と生徒をマッチングするビジネスを自宅で開業することを思い立った
- 在宅医療に移る際、役所の担当者が我が家を何度も訪問し、ヘルパーの時間枠や吸引器・ 補装具の支給を検討してくれた
- 退院時のカンファレンスで、自分だけ制度や流れが分からず置いていかれる気持ちでいたとき、先輩ママがアドバイスをしてくれた
- 一軒家からフラットなマンションに引っ越した。病院で家の前の道路幅やマンションの階数など要件をまとめた書類をもらい助かった
- 三男が退院するときには、夫、当時小学生だった兄たちも病院で2日間の研修を受け、家族内で三男を迎える気持ちがぐっと高まった
- 人工呼吸器のアラーム音が鳴る夢で起きることもある。3時間おきの体位交換やのどが渇いていないかなど、いつも気になっている
- 災害時に向け蓄電池2つと発電機1台を持っているが、それでも電気が止まったときに1日もつかどうかで、電源確保が課題だ
- コロナ禍で家族全員が在宅となり、弟の医療的ケアを家族で分担できた。家族内で感染者が出た場合のシミュレーションもした
- 予定帝王切開で生まれた子どもは呼吸をせず、NICUに運ばれていった。37週で生まれて体重もあり、何とかなると思っていた