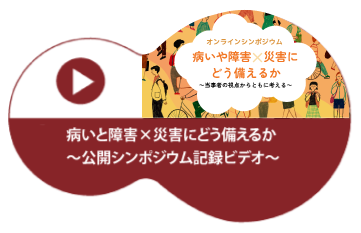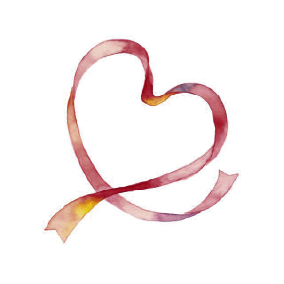周囲の人の支えや関わり
子どもが大きくなり、親は年を取るという順番の中で、親は自分がみられなくなったらと将来への不安を抱えています。
古くからの友人、知人、地域の身近な人と、ふだんからお互いを気にかける関係が維持されることは、日々のケアに追われる親にとって、大切な心の支えになります。
同じような境遇の家族に出会い、地域に必要な制度や自分たちの困りごとを社会に発信していく活動を始めた方もいます。
周囲の人との関わり、支えになったこと、同じ境遇の家族との活動などについて紹介します。
周囲への伝え方
古くからの友人、職場、近所の人に、医療的ケアのあること、障害のあることをどう伝えたのでしょうか。
「かわいそう」と思われるのはつらい、相手も気を遣うだろうと考え、周囲との関係に心を閉ざしたという経験をされた方も少なくありません。
この方は、出産事故でお子さんに障害が残ったことで、旧来の友人との関係の変化を感じたそうです。
次の方は、出産事故でお子さんに障害が残り、当時の友人とは連絡できなくなってしまったと言います。現在は、心から子どもをかわいいと思い、周囲の人にも知ってほしいと、明るく受け答えするようになったそうです。
次の方は、お子さんはストーマを使用しています。日常生活ではあまりなじみのない言葉で、排便というプライバシー度の高い内容であることから、当初は、親族に伝えることもためらいがありました。
現在もきょうだい児のつながりである他の保護者、いわゆるママ友との関係で、病気や医療的ケアの話はできるだけしたくないという気持ちがあるそうです。
次の方は、周囲の子どもたちへの伝え方や反応について語っています。
地域のつながり
地域で子育てしていくにあたり、近隣住民、商店や町会の人、保育園や学校のつながりなど様々な人と関わります。
日常的に医療機器のアラーム音などが鳴ったり、訪問看護などの人の出入りが頻繁であったりするため、ご近所にはできるだけ病気や障害について説明し、挨拶するという方もいました。
この方は、交通事故で重症障害を負ったお子さんが家に戻ってきたときに、近所のお母さんたちに支えられたことについて話してくださいました。
次の方のお子さんは、肢体不自由ですが、中学まで地元の普通学校に通っていました。
学校に通い始めた当時は、車いすでの移動や、食事や排泄介助など必要なことを親が周囲に伝える日々だったそうです。
小学校、中学校と長年、付き合っていくうち、周りの保護者から必要な支援や配慮について意見も出るようになったと言います。
次の方は、国際結婚をしており、ご自身も海外に住んでいた経験もあります。
海外では弱者への周囲の声かけや気遣いを感じていたのに、日本では公共バスで困っていても声をかけられることもなく、あまり関わりを持ちたくない文化の国なのかと感じることもあったそうです。
その中でも、近所のおばあちゃんとのなにげない会話が親子でとてもうれしいとお話くださいました。
次の方は、ご自身の地元にずっと暮らしていて、長男や次男の通う学校や幼稚園で、昔の同級生にも会って話したりするそうです。地域の関わりが、とてもありがたいと言います。
コロナ禍では家族の中に感染者が出ると、医療的ケアのある子が濃厚接触者にあたり、専門職による訪問サービスの提供が中止される時期がありました。次の方は2週間の隔離期間中、周囲の支えがとてもありがたったとお話しくださいました。
次の方は、お子さんが東京オリンピックの聖火ランナーを務めることになり、周りの人がとても喜んでくれたこと、きょうだいの部活動の応援に行って、部員たちや他の家族も一緒になって盛り上がったことを話してくれました。
同じ境遇の家族とのかかわり・支え
子どもの障害や医療的ケアが必要なことが分かり、それからどうしてよいかわからず孤独に悩んでいた方もいます。その中で、同じような境遇にある他の家族と出会い、自分だけではないという思いをもった方、さらに同じように困っている家族が安心して暮らせる社会に向けて活動したという方もいます。
「サービス・情報へのアクセス」の「同じ境遇のママからの情報」 もご覧ください。
次の方は、同じ境遇の親と集まって話していたグループからNPOなどに発展し、医療的ケアや障害のある子を育てる親を支援する活動をしておられます。
自治体を動かす活動へ
医療的ケア児と家族の生活について、行政や議会も実態がよくわからず、なかなか支援が行き届きません。精神的、身体的、経済的な地域のサポートを得るため、地元の議員に陳述を行ったという方について紹介します。
インタビュー当時、この方のお子さんはまだ2歳でしたが、その2年間の子育ての中で感じたインクルーシブ教育の必要や災害対応、制度サポートなどについて、仲間と一緒に自治体に陳情書を提出したそうです。
この方は、お子さんが週3回地域の保育園、週1回療育センターに通っていました。
ある日、次年度から保育園ではなくすべて療育センターに通うように突然言い渡されたといいます。医療的ケアに手厚い療育センターに集約することで、子どもにとっても親にとっても安心な環境というのがその理由だったそうです。
しかし、徒歩10分の保育園から、徒歩30分の療育センターに通う不便さもありました。
事前の相談もないまま決められたことに抗議するために様々な方面に相談したり、声かけをして最終的には撤回してもらうまでの経験をお話くださいました。
2023年7月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 息子に障害があることでどう声をかけたらいいか友人たちも悩んだようだ。話してみると子育ての悩みは同じだといわれ嬉しかった
息子に障害があることでどう声をかけたらいいか友人たちも悩んだようだ。話してみると子育ての悩みは同じだといわれ嬉しかった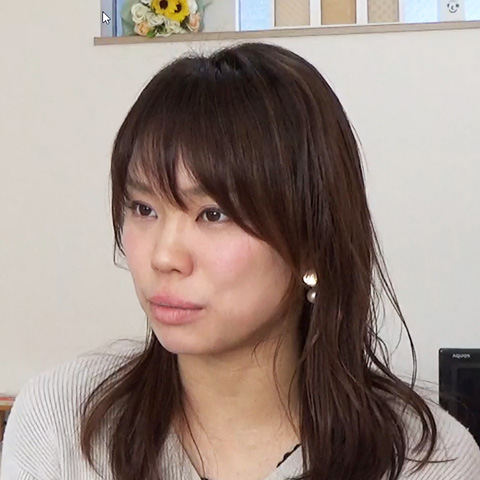 子どもの障害が分かった当時は誰とも話せずにいたが、今は、周囲に知ってほしいと明るく受け答えするように心掛けている
子どもの障害が分かった当時は誰とも話せずにいたが、今は、周囲に知ってほしいと明るく受け答えするように心掛けている きょうだいの友達の質問にグサグサ来たが一つ一つ説明した。子どもたちは大人と違って同情のまなざしはなく未来に希望を感じた
きょうだいの友達の質問にグサグサ来たが一つ一つ説明した。子どもたちは大人と違って同情のまなざしはなく未来に希望を感じた 事故で身体が動かなくなった息子が退院したとき、近所のママたちがクリスマス会を企画し、子どもたちもこれまで通りに接してくれた
事故で身体が動かなくなった息子が退院したとき、近所のママたちがクリスマス会を企画し、子どもたちもこれまで通りに接してくれた 修学旅行は秋芳洞の内部で集合写真を撮る予定だったが、車いすではいけない。周囲の保護者が別の所で撮ればよいと提案してくれた
修学旅行は秋芳洞の内部で集合写真を撮る予定だったが、車いすではいけない。周囲の保護者が別の所で撮ればよいと提案してくれた 子どもと酸素ボンベを背負ってバスに乗っていてもほとんど声をかけられない。その中で近所のおばあちゃんとのなにげない会話がとてもうれしい
子どもと酸素ボンベを背負ってバスに乗っていてもほとんど声をかけられない。その中で近所のおばあちゃんとのなにげない会話がとてもうれしい 自分の地元で暮らし、昔からのつながりがありがたい。子ども同士が無邪気で大人のほうが気遣いばかり、とも感じる (音声のみ)
自分の地元で暮らし、昔からのつながりがありがたい。子ども同士が無邪気で大人のほうが気遣いばかり、とも感じる (音声のみ) 妻が新型コロナウィルスに感染し、1人で娘の2週間の医療的ケアを行うことになった。周囲の友人やきょうだい児のサポートで乗り切った
妻が新型コロナウィルスに感染し、1人で娘の2週間の医療的ケアを行うことになった。周囲の友人やきょうだい児のサポートで乗り切った 心を閉ざしていた自分に声をかけてくれたママと、医療的ケアがあっても嫌なことだけではないと話せたことで自分も強くなれたと思う
心を閉ざしていた自分に声をかけてくれたママと、医療的ケアがあっても嫌なことだけではないと話せたことで自分も強くなれたと思う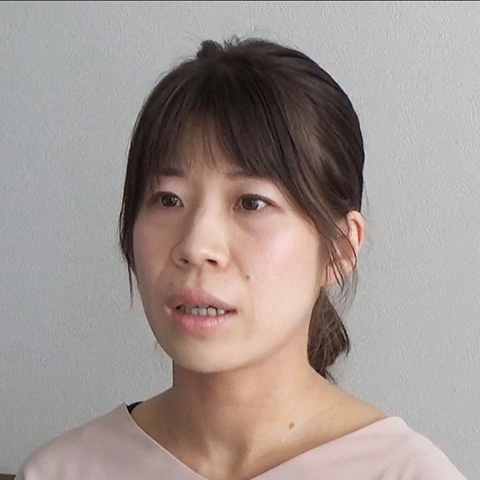 同じ境遇の親に会って、自分も前向きに頑張ろうと思えた。娘も周囲の人を頼りながら、自分に誇りをもって生きてほしい
同じ境遇の親に会って、自分も前向きに頑張ろうと思えた。娘も周囲の人を頼りながら、自分に誇りをもって生きてほしい 同じ境遇の親で集まって当初は泣いていたが、そのうち退院時の相談や親子イベントを開催し、支援活動をするようになった
同じ境遇の親で集まって当初は泣いていたが、そのうち退院時の相談や親子イベントを開催し、支援活動をするようになった 区の福祉センターに医療的ケア児を受け入れてほしいと活動し、実現した。引っ越し先の他区でも重症児のデイサービスを作る活動をする
区の福祉センターに医療的ケア児を受け入れてほしいと活動し、実現した。引っ越し先の他区でも重症児のデイサービスを作る活動をする