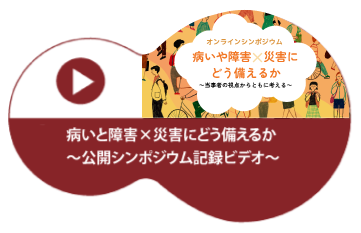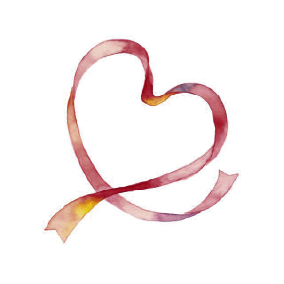子どもの成長と将来への思い
お子さんの成長について「この子は身体は小さいけど、心は大きく育てることができる」という素敵な言葉で表現してくださった方もいました。
生まれてすぐは元気でいることだけをひたすら願っていたのに、子どもが成長するにつれて期待や欲が出てくるのも親心です。
ここでは子どもの成長を感じたことや、現在の子どもへの思い、将来への期待といった思いを紹介します。中には、お子さんの長期的な未来を思い描くことが難しいという方もいますし、障害をもちながら自立することについて社会の受け入れや偏見に対する心配を抱えている方もいます。
子どもの行動から感じる成長
子育てをしていると、子どもが急に大人びた発言や表情をしたり、そんなことができるのと思うような行動があったり、日々親として驚かされることがあります。
まずは、お子さんの行動から成長を感じたというお話です。
この方のお子さんは、2歳からスピーチカニューレ(気管切開をしていながら、発声できる器官カニューレ)で話が少しずつできるようになりました。まだ4歳と小さいながらも、自分が赤ちゃんの頃から頑張ってきたことを認識し、それを誇りに思っている様子をお話くださいました。
次の方は、小学校高学年くらいまで娘の成長の様子があまり見られないと思っていたところ、あるとき急にできることが増えて、身体が育つまでは娘なりに周りの子たちを見て学んでいたのだと感じたと言います。
次の方のお子さんは人工呼吸器を使っていますが、カニューレと呼ばれる管のリーク(空気漏れ)を使って声を出すことができます。身体の成長とともにカニューレを大きくすると、うまく声がでずに悲しい思いをし、細いカニューレの使用を継続しながら、それに伴う乾燥やつまりを防ぐため自分で水分補給を考えて生活している様子をお話くださいました。
子どもとの生活の喜び
医療的ケアのある子は入退院を繰り返し、自分の家で親子の時間を過ごすという当たり前の生活すらほとんど経験できていない子もいます。
親として子どもと生活することの喜びをお話いただきました。
次の方のお子さんは、小学2年生です。生後すぐに深刻な状況を宣告され、先のことは考えていけないと思いながら日々、成長し、ついに就学を迎え、そこまで生き抜いてくれたことへの喜びと感謝をお話くださいました。
お子さんが生まれ生活する中で、自分の知らなかった世界や自分でも知らなかった自分自身に出会えたということに感謝し、これからも活動していきたいとの思いを述べています。
次の方のお子さんは、インタビュー時、生まれてからまだ一度もお家に帰ってきていませんでした。
コロナ禍で生まれたため、お姉ちゃんたちも弟に会うこともできておらず、早く家に帰ってきてみんなで一緒に暮らせる日を心待ちしている気持ちをお話くださいました。
成長に伴う課題と備え
子どもが治療や手術を乗り越えて成長し、どんな将来が待っているのかの期待、学校や社会の中で他人と関わっていくにあたっての心配、お子さんの将来に向けて、どのような準備や訓練を考えているかについてのお話です。
この方のお子さんは、生まれつきの心臓奇形で手術が必要ですが、発達は年齢相応で、外見からケアがあることはわからないそうです。
インタビュー時は1歳でした。2歳で心臓手術をすることで、将来は基本的にはケアのない生活ができることも期待されますが、成長段階で考えることがまだあるそうです。
次の方のお子さんも女の子で、まだ1歳ですが、まずは直近の手術が成功し、口から食べられるようになること、将来は学校で友達と仲良くできるようにしてほしいと思う期待とともに、どこまで自分でできるようになるかは気にかかると言います。
次の方のお子さんはインタビュー時、10歳でした。第二次性徴に伴い、これまでなかった身体やこころの症状が出てくることが心配だとおっしゃっています。側弯を矯正するリハビリとして親子で体操をして将来に備えているそうです。
次の方のお子さんは、インタビュー時29歳。これまで小児科にかかっていたところ、成人期に入り、大人向けの診療科への移行を始めたということです。
次の方のお子さんも成人ですが、インタビュー当時は小児科がかかりつけ医の頃でした。成人医療への移行をしなければと思いながら、コロナ禍もあり、移行が進んでいないとお話くださっています。
大人になるということ
子どもから大人へ。医療的ケアがありながら、我が子が将来どうやって生きていくのか、一人で生きていけるのか、というのは多くの親に共通する悩みです。
誰かのケアが必要だからこそ成人となったときの生活を考えないといけないけれど、今は想像できない、想像したくないという声もありました。
次の方は子供の成長を喜びながらも、子どもを独りあとにのこすより、自分が看取ったほうがいいと思ったこともあったと語っています。
インタビュー時、中3の娘さんをお持ちの方は、将来は周りに助けを求めることが多いので、言葉遣いや清潔に気をつけ、丁寧に「ありがとう」を言える子になるよう日頃から伝えているとおっしゃっていました。
導尿を自力でもできることようになることで、将来、自立できるように訓練していきたいともお話くださいました。
自立に向けたお子さんの取り組みや頑張りについてもお話しいただきました。
この方のお子さんは、会話もできますが、大きな声は出しづらいことや慣れていないこともあり、なかなか人前で話すことはありませんでした。
しかし、将来は一人暮らしという目標をもち、ヘルパーさんと会話するようになったそうです。
次の方は娘さんが成人してからどう社会に貢献していくべきかを考え、本人に選挙権を行使することを意識付けてきたそうです。
この方のお子さんは7週に1回生物学的製剤の投与を受けていますが、投与するだけで3時間、移動や準備、待ち時間などを入れるとほぼ半日かかかります。将来、子どもが自立し、仕事をすることについての悩みや不安をお話くださいました。
公共交通機関、事業所、病院といったインフラが豊富ではない地域に住んでいる人特有の悩みもあります。
次のご家族は、移動手段が車中心の地域にお住まいです。親が高齢になって自家用車で動けなくなった時のことを考え、子どもが将来、自力で公共のバスを使って移動できるようにしなければと考えています。
次のご家族も将来、障害のある子が地域で安心して暮らせる環境を望んでいるが、現状、事業所の確保が難しくサポート体制への不安があるといいます。
2023年7月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 これから補装具を作る子に、補装具を付けて歩く様子を見せてほしいと息子が頼まれ実演したとき、息子の表情が誇らしげで嬉しかった
これから補装具を作る子に、補装具を付けて歩く様子を見せてほしいと息子が頼まれ実演したとき、息子の表情が誇らしげで嬉しかった 娘は中1頃から反抗的な行動もある一方、洗濯物を畳んだり、家族のために自分ができることを探してくれたり成長を感じる
娘は中1頃から反抗的な行動もある一方、洗濯物を畳んだり、家族のために自分ができることを探してくれたり成長を感じる 娘は小学校高学年まで積極的な様子がなかったが、身体が成長すると急にボールつきをしたり、学習意欲があふれてきて驚いた
娘は小学校高学年まで積極的な様子がなかったが、身体が成長すると急にボールつきをしたり、学習意欲があふれてきて驚いた 娘はカニューレのリーク(空気漏れ)で発話ができる。管の乾燥やつまりを娘本人が理解し、介助者に水分を積極的に要求している
娘はカニューレのリーク(空気漏れ)で発話ができる。管の乾燥やつまりを娘本人が理解し、介助者に水分を積極的に要求している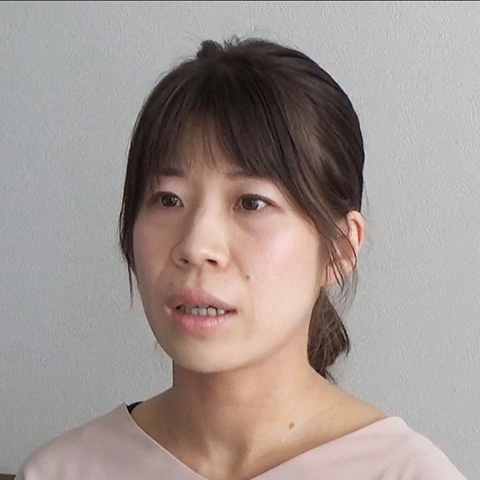 何度も辛い思いをしながらも成長する娘は、「生きること」そのものを教えてくれる。うちの子で生まれてくれてありがとうと思う
何度も辛い思いをしながらも成長する娘は、「生きること」そのものを教えてくれる。うちの子で生まれてくれてありがとうと思う 息子は小学2年生になった。ここまで息子なりに成長してくれたことに感謝しかない。次の目標は10歳の誕生日を盛大に祝うことだ
息子は小学2年生になった。ここまで息子なりに成長してくれたことに感謝しかない。次の目標は10歳の誕生日を盛大に祝うことだ 息子が障害をもって生まれたことで自分の中の差別意識に気づき、障害者差別をなくす活動につながっている。息子には感謝の思いだ
息子が障害をもって生まれたことで自分の中の差別意識に気づき、障害者差別をなくす活動につながっている。息子には感謝の思いだ 娘は2歳で心臓手術ができそうだ。手術を乗り越えて成人期を迎えることになっても妊娠への影響など心配なことは残っている
娘は2歳で心臓手術ができそうだ。手術を乗り越えて成人期を迎えることになっても妊娠への影響など心配なことは残っている 染色体異常の子は第二次性徴に伴い、身体やこころに新たな症状が出てくるようで、娘は側弯(そくわん)が強く出ている
染色体異常の子は第二次性徴に伴い、身体やこころに新たな症状が出てくるようで、娘は側弯(そくわん)が強く出ている 29歳の娘はぜんそくの発作や、コロナワクチン接種をきっかけに、小児科から大人の診療科の受診を勧められ、移行期間中だ
29歳の娘はぜんそくの発作や、コロナワクチン接種をきっかけに、小児科から大人の診療科の受診を勧められ、移行期間中だ 田舎でバスの本数も少ない。将来息子が大人になったときに公共交通機関を使って自力で移動できるよう、定期的に経験させている
田舎でバスの本数も少ない。将来息子が大人になったときに公共交通機関を使って自力で移動できるよう、定期的に経験させている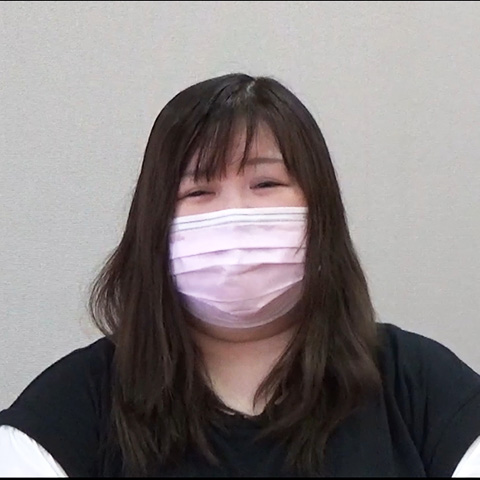 将来、障害のある次女も地域で自立して暮らせる在宅環境を願っているが、田舎で事業者や病院がなく、民生委員との連携もなく不安だ
将来、障害のある次女も地域で自立して暮らせる在宅環境を願っているが、田舎で事業者や病院がなく、民生委員との連携もなく不安だ