入試の準備と実際
大学入試には、様々な準備が必要です。その中でも障害を持つ学生は、入試に際して、配慮が必要になることもあります。ここでは、入試に向けた準備と、実際の入試の配慮について、また、入試の時に大学に自分の障害を伝えることについて、それぞれの語りを紹介します。
入試に向けた準備
日本では2010年頃から入試の方法が多様化し、一般入試が減り、AO入試(アドミッションズ・オフィス入試:学力試験ではなく高校の成績や小論、面接などで人物を評価して入学の可否を決めるもの)や推薦入試の割合が増加しています。インタビューに答えた人たちも、AO入試や推薦入試で受験した人が多くいました。
AO入試や推薦入試では、学力に関すること以外にも、出願までに様々な準備が必要です。次の車椅子の女性は、推薦入試に向けて行った準備について、語っています。
AO入試の中でも、様々な種類があります。次の人は、それぞれの入試で求められる内容を平行して準備をした体験を、語っています。
推薦入試の場合は、高校の内申点が、出願の条件や合否の基準になることがあります。推薦入試で受験をした人の中には、「高校の成績を良くするため、定期試験の点数を上げられるように努力した」と語った人がいました。
また次の人は、推薦入試に向けて内申点を上げる必要があるのに、障害のために高校の体育の成績がネックだったことについて、語っています。
推薦入試やAO入試が増えている一方で、一般入試で受験をする人も多くいます。次の弱視の女性は、一般入試の準備のために通った学習塾や参考書選びについて、語っています。
さらに、推薦入試やAO入試、医療系の学部の入試など、入試に面接がある場合もあります。看護学部の受験を目指していた次の吃音の男性は、入試の面接の準備について話していました。
入試の配慮
入試当日は、事前に配慮申請をして、配慮を受けながら試験を受けた人が多くいました。インタビューに答えた人の中には、「特別支援学校は、大学入試の配慮申請に慣れている」と言う人もいましたが、普通学校で、「高校の先生と要望内容をまとめて、大学に提出した」という人もいました。また、入試の際に配慮申請ができることも知らないまま、受験をした人もいました。
次の2人は、入試の際の配慮申請について、出身校のかかわりを語っています。
入試当日に受けた具体的な配慮内容について、次の4人は、実際に自分の障害に合った配慮を受けた体験を語っています。
障害のことを伝えて受験した人の中にも、次の2人のように、当日試験に行ってみて自分が思うような配慮内容ではなかったり、実際の試験で困ることがあったりした人もいました。
受験先に障害について伝える/伝えない
インタビューに答えた人たちの多くは、試験で配慮を受けるために前もって自分の障害のことを大学に伝えています。しかし、障害について大学に伝える思いや、あえて伝えなかった理由についても、様々なことが語られました。
高校卒業までごく限られた人にしか聞こえないことを伝えてこなかったという聴覚障害の女性は、「大学に入ったら、ありのままにやりたいことをやろうと思って、大学に聞こえないことを伝えた」と語っていました。
次の人は、入試に配慮は必要ありませんでしたが、あえて願書の備考欄に自分の障害について書いた時の思いについて、語っています。
次の難聴の女性は、センター入試では申請して配慮を受けましたが、一般入試については配慮の申請をしなかったことを話しています。
インタビューに答えた人は、20代~40代と幅があります。合理的配慮が意識されなかった時代に受験した40代の男性は、自分の障害のことを事前に伝えずに受験して、そのことを責められた経験について、語りました。
2021年1月公開 2022年4月更新
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 推薦入試のための作文は、高校の先生に問題を準備してもらい見てもらった。面接も、何人かの先生に練習をしてもらって本番に臨んだ
推薦入試のための作文は、高校の先生に問題を準備してもらい見てもらった。面接も、何人かの先生に練習をしてもらって本番に臨んだ 予備校は、集団だと難しいと思ったので個別指導の学習塾を選んだ。参考書も、自分が見やすいものを選んでいた
予備校は、集団だと難しいと思ったので個別指導の学習塾を選んだ。参考書も、自分が見やすいものを選んでいた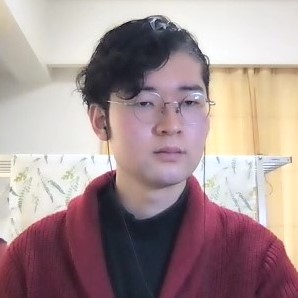 面接は吃音の症状でどうしても詰まってしまうので、高校の先生に何回も練習してもらった。とても大変だった思いがあるが、その分、他の試験科目でカバーしようとも思っていた(NEW)
面接は吃音の症状でどうしても詰まってしまうので、高校の先生に何回も練習してもらった。とても大変だった思いがあるが、その分、他の試験科目でカバーしようとも思っていた(NEW) 聴覚障害があるが、高校まで普通学校で、配慮や支援について何も知らなかった。センター入試で初めて配慮のことを知って申請し、個別の試験でも別室受験などの配慮を受けた
聴覚障害があるが、高校まで普通学校で、配慮や支援について何も知らなかった。センター入試で初めて配慮のことを知って申請し、個別の試験でも別室受験などの配慮を受けた 20年以上前の当時は、点字受験を認めているところしか受験せず、時間も“点字受験イコール1.5倍の時間延長”とほぼ決まっていたので、事前に大学側と交渉することはなかった
20年以上前の当時は、点字受験を認めているところしか受験せず、時間も“点字受験イコール1.5倍の時間延長”とほぼ決まっていたので、事前に大学側と交渉することはなかった 入試の際は、全部の大学に、自分はろう者だと伝えていた。試験では、試験官が話す内容を紙に書いてもらい、面接ではゆっくり話してもらった(手話)
入試の際は、全部の大学に、自分はろう者だと伝えていた。試験では、試験官が話す内容を紙に書いてもらい、面接ではゆっくり話してもらった(手話) 肢体不自由のために、別室受験と時間延長などの配慮を受けた。拡大されたマークシート用紙が扱いにくく、2年目はクリップを持ち込んだ
肢体不自由のために、別室受験と時間延長などの配慮を受けた。拡大されたマークシート用紙が扱いにくく、2年目はクリップを持ち込んだ 面接では最初に自分で話し、言語障害のためにうまく伝わらない部分をパソコンで入力して伝えた
面接では最初に自分で話し、言語障害のためにうまく伝わらない部分をパソコンで入力して伝えた 事前に聴覚障害のことを大学に伝えたところ、英語のリスニング試験でいきなり、英単語の間のスペースを除いた英文を渡され、あとは全て他の学生と同じでとても困った
事前に聴覚障害のことを大学に伝えたところ、英語のリスニング試験でいきなり、英単語の間のスペースを除いた英文を渡され、あとは全て他の学生と同じでとても困った 脳性まひによる体の緊張で汗をかきやすいが、面接ではヘルパーや母親の同席は認められず、汗がたくさん流れて大変だった
脳性まひによる体の緊張で汗をかきやすいが、面接ではヘルパーや母親の同席は認められず、汗がたくさん流れて大変だった クローン病であることは、願書の備考欄にはっきり書いた。それで落とされるなら、そこの大学には行かないと思っていた
クローン病であることは、願書の備考欄にはっきり書いた。それで落とされるなら、そこの大学には行かないと思っていた 障害がマイナスになってしまうのではないかと思い、また全く聞こえないわけではなかったので、一般入試では障害のことを伝えずに受験をして、周囲の(NEW)
障害がマイナスになってしまうのではないかと思い、また全く聞こえないわけではなかったので、一般入試では障害のことを伝えずに受験をして、周囲の(NEW) 障害のことを伝えずに受験をしたら、試験終了後に「なんで障害があるのに黙って受けたんだ?」と言われたこともあった
障害のことを伝えずに受験をしたら、試験終了後に「なんで障害があるのに黙って受けたんだ?」と言われたこともあった



