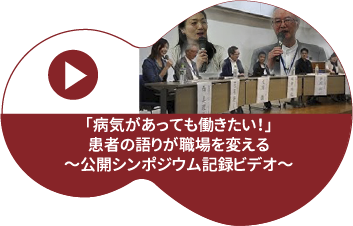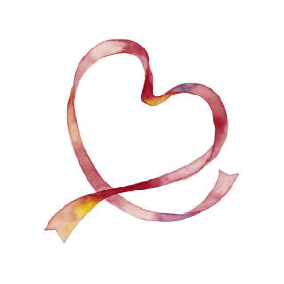家族との関係
ここではクローン病が家族間の人間関係に及ぼす影響についての語りをご紹介します。クローン病は10代~20代で発症することの多い病気です。診断時点ではまだ親と同居している人も多いため、最初に影響が出るのは本人の親との関係です。成人してから自分の家族を持つようになると、今度は配偶者やパートナーとの関係、さらに自分の子どもとの関係に病気が影響を及ぼす、あるいは関係性が病気に影響を及ぼすことがあります。
自分の親とのかかわり
クローン病と診断され、それが難病だということを知ったとき、多くの親はショックを受け、何かと心配します。12歳で発症したという次の男性は、両親が何とかして治してやろうと、民間療法や宗教にも頼ったりしたことを思い返し、感謝の気持ちを語っています。
20代に入ってから発症した人でも、親と同居していたり、近所に住んでいたりして、いろいろ親が気遣ってくれたことを振り返っています。一方、診断時には既に一人暮らしをしていたので、両親は深刻な病気だということをよくわかっておらず、心配してもらえなかったと話す人もいました。
病気が原因で親子の関係がぎくしゃくしてしまうこともあるようです。15歳の時に診断を受けた女性は、そのときの両親の反応が原因で親との間に確執が生まれてしまったといいます。また、19歳で発症して33歳になるまで診断がつかなかったという女性も、当初両親は心配してくれたものの、食事や受診のタイミングについて批判されたことで、関係がこじれてしまったこともあったと話しています。本人も病気になったのは親のせいではないとわかっていても、つい親にあたってしまうということがあるようです。ただ、そうした経験をした人でも、多くの場合は時間とともに次第に関係性は修復されていったと話していました。
同じ親でもこのように母親と父親で病気に対する反応の仕方は異なり、特に母親は健康な体に産み育てられなかったことに責任を感じて自分を責めることが多いようです。そしてそのことに気が付いた患者本人もまた傷ついていました。
一方で母親が働いていて食事を作ってもらえなかったことを発症の原因と考えて、母親を責めたという人もいました。母親は治療費は出すがあとは「自分で頑張って生きなさい」という姿勢だったと振り返っています。
10代前半で発症した患者は通常、当初は親に連れられて医療機関を受診していますが、ある時点で親から自立して、自分で治療方針などを決めていかなくてはなりません。次の方は中学生のころから一人で受診するようになり、自分で考えて病気に向かいあってきたそうです。
配偶者や子どもとの関係
病気は夫婦関係にどんな影響を与えるでしょうか。32歳で診断を受け、35歳の時に結婚した女性は、病気が原因で離婚する人もいる中で、夫がずっと病気と付き合ってくれたことを感謝しています。19歳で発症した男性は、母親が食事を作るのに悩んでいたことを思い、妻には食べ物のことではなるべく負担をかけないようにと気遣っていました。
自分の病気について、子どもに説明するかどうかというのは、ストーマや経鼻栄養のチューブのように見た目でわかる治療を受けている場合とそうでない場合とで状況が違ってきます。子どもが生まれてからは一度しか入院しておらず、普段の生活でも子どもとはすれ違いだったという男性は、病気のことは子どもにはあまりはっきりと話していませんでしたが、幼い子どもを持つ母親は普段から自分が鼻から栄養剤を入れているのを見ている子どもに対して「お母さんはおなかの病気」と伝えるようにしていました。
次の男性は子どもたちが小学生の時に直腸がんのためストーマ(人工肛門)をつけましたが、その後は一緒にお風呂には入っていません。ストーマを説明することよりも父親ががんになったことを伝えるのが難しいと話しています。
次の男性は、体調が悪くてもよそのお父さんと同じように野球の応援に出かけ、キャンプ料理も工夫しながら家庭サービスを心掛けていました。
次の方は自ら患者会を立ち上げましたが、それが新聞に掲載されて子どもが学校でいじめられたということがありました。子どもにとってもつらい経験だったでしょうが、この方にとっても複雑な思いがありました。
2019年6月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 両親は私のことをとても心配して、民間療法や宗教のところに相談に行ったりしていた。それはやはり息子の病気を治したいという思いが強かったからだと思う
両親は私のことをとても心配して、民間療法や宗教のところに相談に行ったりしていた。それはやはり息子の病気を治したいという思いが強かったからだと思う 長い間両親と3人で暮らしていたので、病気になってから両親はとても心配してくれた。途中ぎくしゃくしたこともあったが、今では母親には感謝している
長い間両親と3人で暮らしていたので、病気になってから両親はとても心配してくれた。途中ぎくしゃくしたこともあったが、今では母親には感謝している 40度の熱が出て緊急入院した時、両親は遺伝的なものかと心配した。結婚式の1か月前だったので、式に出られるのか心配し、相手の両親にも申し訳ないと思っていたようだ
40度の熱が出て緊急入院した時、両親は遺伝的なものかと心配した。結婚式の1か月前だったので、式に出られるのか心配し、相手の両親にも申し訳ないと思っていたようだ 診断を受けた時はもう一人で暮らしていたので、両親はそれほど病気にかかわっていなかった。当時はもう少し心配してくれてもいいと思った
診断を受けた時はもう一人で暮らしていたので、両親はそれほど病気にかかわっていなかった。当時はもう少し心配してくれてもいいと思った 両親は難病という言葉を聞いて絶望感を抱いた。母親からは「そんな体に産んでごめんね」と言われたが、慰められるっていうよりもすごく傷ついた記憶がある
両親は難病という言葉を聞いて絶望感を抱いた。母親からは「そんな体に産んでごめんね」と言われたが、慰められるっていうよりもすごく傷ついた記憶がある 看護師だった母親からはひどくなるまで我慢したことや食生活についてうるさく言われた。父親は診断を聞いて悲しんでいたが、今でも食事制限のことは理解できていないようだ
看護師だった母親からはひどくなるまで我慢したことや食生活についてうるさく言われた。父親は診断を聞いて悲しんでいたが、今でも食事制限のことは理解できていないようだ 母親は、私には直接何も言わなかったけれど、自分を責めて泣いていたという話を妹から聞いた。父がそういうことを責めるタイプの人だったので、父には病気のことは話していなかったと思う
母親は、私には直接何も言わなかったけれど、自分を責めて泣いていたという話を妹から聞いた。父がそういうことを責めるタイプの人だったので、父には病気のことは話していなかったと思う 母親が「自分の娘が病気になって普通のご飯さえ食べられないのに何もできないっていうのは本当に辛いんだ」と言って泣いた時に、本当は支える側のほうが辛いんだということに気が付いた
母親が「自分の娘が病気になって普通のご飯さえ食べられないのに何もできないっていうのは本当に辛いんだ」と言って泣いた時に、本当は支える側のほうが辛いんだということに気が付いた 主人と結婚するときに当然病気のことは話したが、「別に構わない」と言ってくれた。調子が悪い時は主人が家事を分担してくれる。あまり深刻にならないタイプなのもよかった
主人と結婚するときに当然病気のことは話したが、「別に構わない」と言ってくれた。調子が悪い時は主人が家事を分担してくれる。あまり深刻にならないタイプなのもよかった 食事に関しては、家内の負担にならないように特別な配慮はしなくていいと言ってあるので、子ども中心の食事で、自分は食べられるものを選んで食べている
食事に関しては、家内の負担にならないように特別な配慮はしなくていいと言ってあるので、子ども中心の食事で、自分は食べられるものを選んで食べている 子どもには自分の病気についてあまりきちんと話したことはないし、外見ではわからないのであまり理解していないと思う
子どもには自分の病気についてあまりきちんと話したことはないし、外見ではわからないのであまり理解していないと思う 子どもはお母さんが鼻から栄養剤を入れたり、病院に行ったりするというのはわかっているので、「おなかを診てもらいに病院に行く」というように普通に話をしている
子どもはお母さんが鼻から栄養剤を入れたり、病院に行ったりするというのはわかっているので、「おなかを診てもらいに病院に行く」というように普通に話をしている 二人の男の子がいるので体調が悪くても家庭サービスには努めていた。キャンプなどにも食事を工夫しながらよく出かけた
二人の男の子がいるので体調が悪くても家庭サービスには努めていた。キャンプなどにも食事を工夫しながらよく出かけた 患者会を立ち上げた時に新聞に取り上げられたが、子どもが学校でいじめられて、家内からも「あなたが患者会なんかするから、家族は惨めな思いをする」といわれた
患者会を立ち上げた時に新聞に取り上げられたが、子どもが学校でいじめられて、家内からも「あなたが患者会なんかするから、家族は惨めな思いをする」といわれた