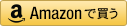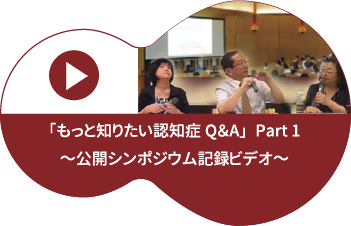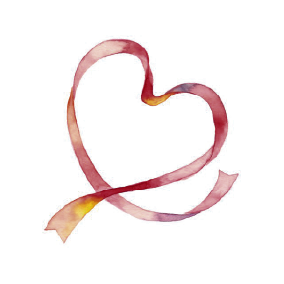認知症本人の家族への思い
ここでは認知症ご本人の家族に対する思いをご紹介します。
パートナーに対する思い
家族の中の関係性も病気の診断を受けて変化して行きます。特に若年性認知症では、現役で働いていた夫が認知症になった場合、夫婦間の性別役割にも変化が起こり、双方とも思うようにいかないことにストレスがたまって衝突することもあります。病気になる前はいわゆる「亭主関白」だった男性は、そんなときに自分の方から折れて謝ったり、妻にマッサージをしてあげたりすることで、夫婦の関係を良好に保っていく努力をしていると話しています。
一方、次の男性は、自分が何かをしようとしているときに、妻が先回りしてやってくれることがかえって負担になってしまい、かっとなって家を飛び出してしまうこともあったと話しています。男性の妻は、医師として働いていた頃の夫は大変多忙だったので、何でも先回りして用意するのが「いい奥さん」だと思っていたが、このインタビューを聞いて「はっとした」と話していました。
若年性レビー小体型認知症の女性は、一人で受診して診断を受けたのですが、認知症という診断は本人だけでなく配偶者にも絶望感を抱え込ませることになるという思いから、診断結果をなかなか夫に伝えることができず、その間はとても孤独だったそうです。診断を伝えた後は、夫がさりげなく気遣って支えてくれることをありがたく思っています。
診断当初は、夫から「俺の老後はどうなるんだ」と責められたという若年性レビー小体型認知症の女性も、今は認知症当事者への支援活動に理解を示し、息子とともに応援してくれていると話してくれました。
家族へのインタビューでは、元気な頃は言葉で愛情表現をすることがなかった夫が、病気になってからは「結婚してよかった」とか「愛してるよ」といった言葉を口にするようになったと話している人たちがいました。
認知症が進んでくると、次第に言葉でのコミュニケーションが難しくなってきますが、家族はちょっとした仕草にご本人の気持ちを読み取っています。次の男性は言葉が出なくなった妻が、下の世話をしてもらう時に夫の頭をなでようとするのを妻の愛情表現と受け止めていました。
子どもに対する思い
私たちのインタビューでは、同居しているか否かに関わらず、高齢の認知症の女性たちは娘と密接な関係を持っており、認知症のために娘に世話をかけていることについて申し訳なく思っていて、娘のためにもっとしっかりせねば、と話していました。
体調を崩して入院していた高齢の女性は、認知症の診断がつく前から、娘に対して「私のことはいいから」と、いつも母としての気遣いを見せてくれていたそうです。
シングルマザーとして二人の子どもたちを育ててきた女性は、認知症の診断を受け、子どもたちの将来を考えて「一瞬」離婚したことを後悔した、と話していました。けれども、娘と息子の、それぞれに母親を思う気持ちを思いやりながら、前向きに生きて行こうという決意を語っています。
また、別の若年性認知症の女性は、成人している子どもたちに診断を伝える際には「希望とセットで」伝えたいと思い、認知機能の低下は個人差があるので、進行しないように努力すると話したところ、逆に子どもから「歩けなくなったら車椅子に乗ればいい」といわれ、日々進行を恐れて生きていた自分に気づかされたと話しています。
その他の家族に対する思い
次の若年性認知症の男性は母親も認知症で、グループホームで生活していますが、その母の様子が一番気になると話しています。時折電話をかけてくる母の記憶障害が進んでいることが悲しいと話していました。
中には身近な家族がいない認知症の人もいます。次の男性は妻と離別して2人の娘や孫とも会っておらず、兄とも連絡を取っていません。しかし、むしろ家族がいなくて良かったと話していました。
2021年7月更新
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 元気な頃は「おい」「飯」というだけだったが今は必ず笑顔で「ありがとう」という。今は「ごめんなさい」を言う練習もして、妻とぶつかっても自分が叱られて終わるようにしている
元気な頃は「おい」「飯」というだけだったが今は必ず笑顔で「ありがとう」という。今は「ごめんなさい」を言う練習もして、妻とぶつかっても自分が叱られて終わるようにしている 最近はあまりけんかもしないが、以前は自分が何かしようというときに、妻が先回りして何かやったり言ったりするのが嫌で、「がっ」となって家を出て行くときもあった
最近はあまりけんかもしないが、以前は自分が何かしようというときに、妻が先回りして何かやったり言ったりするのが嫌で、「がっ」となって家を出て行くときもあった 認知症という診断は本人だけでなく配偶者にも絶望感を抱え込ませることになると思うので、夫に対して自分の症状について話すことはなかった(音声のみ)
認知症という診断は本人だけでなく配偶者にも絶望感を抱え込ませることになると思うので、夫に対して自分の症状について話すことはなかった(音声のみ) 妻の下の世話をしているときに頭をなでてくれるのはありがとうの意味だろう。妻は言葉には出せないが、自分が介護で愛を注いでいることはわかってくれていると思う
妻の下の世話をしているときに頭をなでてくれるのはありがとうの意味だろう。妻は言葉には出せないが、自分が介護で愛を注いでいることはわかってくれていると思う 認知症のためにへまばっかりしていて娘に迷惑をかけているので、もっとしっかりしないといけないと思っている
認知症のためにへまばっかりしていて娘に迷惑をかけているので、もっとしっかりしないといけないと思っている 母は、まるでこうなっていくことがわかっていたかのように、「子どものことをしっかり見て、私のことなんかいいから…前を向いて生きていきなさい」と言っていた
母は、まるでこうなっていくことがわかっていたかのように、「子どものことをしっかり見て、私のことなんかいいから…前を向いて生きていきなさい」と言っていた 娘が頼んだことをやってくれないのは母親の病気を受け入れられずに苦しんでいたからだった。元気に外に出掛けていく姿を見せることが娘にとってもいいことではないかと思う
娘が頼んだことをやってくれないのは母親の病気を受け入れられずに苦しんでいたからだった。元気に外に出掛けていく姿を見せることが娘にとってもいいことではないかと思う