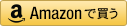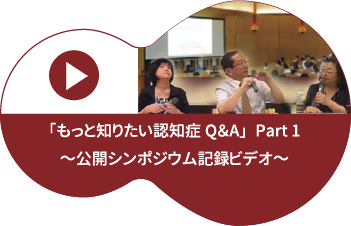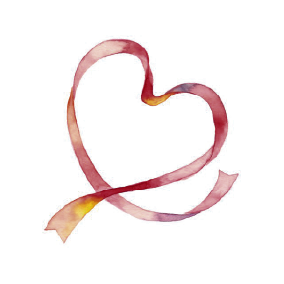家族内の介護協力
認知症の症状が進行すると在宅における介護には、何らかの支援や協力が必要となります。公的支援や民間サービスの利用については“経済的負担と公的な経済支援制度”で説明しますが、ここでは、家族内の介護協力に関する語りを紹介します。介護を主に支える人の決定や誰がどのような内容の協力ができるかについては、家族構成、家族の居住地・職業・健康状態などによって影響を受けていました。また、認知症の人の病状によっても介護する家族の役割の変更を余儀なくされていました。ここでは、家族内の介護協力に関する語りを、きょうだいで親を介護する、一人っ子が親を介護する、舅・姑を介護する、配偶者を介護するに分けて紹介します。
きょうだいで親を介護する
今回、インタビューに答えてくださった人たちの中には、同居して認知症になった親を介護している人たちと、通いで介護に協力している人たちがいました。同居していても、まだ軽症の場合、他のきょうだいがたまに訪ねてくれたり、電話で愚痴がこぼせたりするだけでもありがたいと話している人たちがいました。しかし、介護度が上がると、同居で主に介護していた人たちの中には仕事との両立が困難で、施設入所を決意した人たちがいました(「施設入所を決める」 参照)。中には、介護を主に支える人の役割を別のきょうだいから引き継ぐ選択をした人もいました。次に紹介する女性は、母親と同居したきっかけや同居後の夫への気遣いについて話しています。
通いで親の介護をしている人たちの中には、姉妹で協力して介護にあたっている人や、男女のきょうだいで協力しながら、介護を主に支える兄嫁をサポートしているという人たちがいました。日程を組み、それぞれの得意分野を活かすなど、複数での介護協力の現状について語っていました。
また、通いで協力するといっても、遠方に住んでいたり、仕事や家庭の事情で頻繁に通えない人たちもいました。ある女性は、月に1-2回しか行けず、当時、母と同居していた妹の気持ちをくむことができなかったことやたまに会う母への対応の難しさを語っています。妹が一旦、家を出ることになった経緯については、「対応に困る言動:不穏(不安等で落ち着かない様子)・暴力(乱暴な振舞い)・妄想・幻視」インタビュー家族19をご参照ください。
きょうだい間の協力体制や調整があまりうまくいっていないと話す人たちもいました。認知症の両親を通いで見ている女性は兄と不仲になってしまったと話しています。認知症の親が夫婦暮らしまたは独居の場合、今後のことについての見解の違いで調整に時間がかかっているという人(「施設入所を決める」インタビュー家族10 参照)もいました。
通いで介護に協力している人たちは、中心となって親の介護を担ってくれている家族への気遣いや心配について次のように語っています。
また、嫁ぎ先から通って実家の両親の介護にあたっている人は、嫁ぎ先への気遣いがあると話していました。
自分の母親と夫の父親を引き取って暮らせるように、中古住宅を買い取ってバリアフリーに改築したという女性は、3人きょうだいの末っ子の自分が母の面倒を見ることになったのは運命だったのではないか、と話しています。
一人っ子が親を介護する
インタビュー協力者の中には、一人っ子で親を介護していた人たちがいました。ある女性は、一人っ子だときょうだいの協力がない分、割り切って他者に頼むことができると話していました。彼女は、当初介護にあたっていた母親にがんが見つかり、父の介護と母の看病をいっぺんに担わなくてはならなくなり、戸惑ったという話もしています。現在は結婚してスープの冷めない距離に住んで、父の介護をする母をサポートしているそうです。
次に紹介する一人っ子の女性は、同居していた両親が認知症となり、介護に取り組んだ経験やそのときの夫や子どもの様子について語っています。一度に2人を介護することの大変さから、母親は施設入所することになります。この語りは「施設入所を決める」(インタビュー家族34) を参照してください。
舅・姑を介護する
インタビューに答えた人の中で、嫁の立場で義父・義母を介護した経験のある人は5人でした。実の両親を介護することに比べ、遠慮やストレスを感じる、かえって冷静でいられる、実の親子である夫や夫のきょうだいに役割を期待してしまう、意見の違いを感じることがあるなどの経験を語っていました。ある女性は、実の両親が先に認知症となったので、経験を活かして介護しているが、舅は実の親とは違うので、きついことは言えないし、下の世話などストレスはあると話していました。彼女は義姉との関係についても話しています。
夫との関係について、姑の介護の不満や愚痴ばかり言うと、喧嘩になってしまうことがよくあったという人がいました。後に、知り合いの紹介で施設に入所することになりましたが、夫の本当の気持ちはどうなのかと考えることもあるそうです。夫との立場の違いについて次のように話しています。
舅・姑にとって孫にあたる娘や息子たちの存在が助けになったと話す人たちもいました。
配偶者を介護する
配偶者の介護の場合、介護する人の年齢によって、状況に違いがありました。
インタビューに協力した若年性認知症の人を介護する配偶者の多くは、ほぼ一人で介護にあたっていました。子どもがいない、あるいは子どもは遠方にいて夫婦2人暮らしというケースもありますが、多くは同居や近所に子どもがいる場合でも、子どもたちは介護そのものというよりも機会を見つけて訪ねたり、介護者の愚痴を聞いたり、認知症や介護に関する情報を得てきたりといったサポートが中心となっていました。認知症の父を介護する母のサポートで週末、実家を訪れていたという女性は、娘が3人いて同居できなかったのは親不孝だったような気もするが、同居していないことで父に優しくできたのかもしれない、と話していました。
次の女性は夫が突然仕事をやめてしまったことを機に資格を活かして訪問ヘルパーの仕事につきますが、夫が前頭側頭型認知症と診断され要介護度が上がると、ヘルパーの資格を持つ娘に協力を頼み、仕事を継続しながら二人三脚で在宅介護を継続することができました。
次に紹介する認知症の妻を介護する男性は子どもがなく、仕事を続けながら介護するために、義母の協力を得たと話しています。
今回のインタビューでは認知症の夫や妻のきょうだいの介護協力について話していた人はいませんでしたが、義母の介護中に夫が若年性認知症になってしまったために、義母の介護を一時的に義弟が引き受けていた、という人がいました(「施設入所を決める」インタビュー家族15 を参照)。
一方、認知症高齢者を介護する配偶者は、ご自身も高齢であることが多く、同居の家族がいない場合は、いわゆる「老老介護」と呼ばれる状況になります。今回のインタビューでは、高齢の夫婦二人世帯で介護している人たちは、福祉を担う制度や施設等(社会資源)を活用しながら、ほぼ自力で介護しており、特に子どもたちの介護役割については語っていませんでしたが、今後自分も病気になったりしたときに子どもたちに頼るのかどうかといった将来への懸念を語っていました。
子どもと同居している場合は、必要に応じて協力を得ている人もいれば、子どもが主として介護している人もいました。認知症の妻の面倒を見ている男性は、病院へ行くときは専門的なことがわからないので、離れに住む息子夫婦に同行してもらっている、と話していました。また、夕食は息子たちと一緒に食べているそうです。認知症の妻と次女と同居している男性は、自分の役割を妻と娘たちの関係の調整役だと話していました。
2021年7月更新
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 去年くらいから母の足腰が弱くなり、生活面の介助が必要となってきた。妹は仕事を辞めるわけにはいかないので、それまで妹と暮らしていた母を引き取って介護している
去年くらいから母の足腰が弱くなり、生活面の介助が必要となってきた。妹は仕事を辞めるわけにはいかないので、それまで妹と暮らしていた母を引き取って介護している 当初は、三姉妹が通いで2人暮らしの両親を見ていた。遠方に住む妹たちとの役割分担は性格や仕事の状況を加味して、1人に集中しないよう半年くらいの日程を組んで介護した
当初は、三姉妹が通いで2人暮らしの両親を見ていた。遠方に住む妹たちとの役割分担は性格や仕事の状況を加味して、1人に集中しないよう半年くらいの日程を組んで介護した 普段、同居の兄嫁が母を介護しており、姉が通って手伝っている。自分や妹も時々行って世話をする。男のきょうだいも直接ケアはしないが、送り迎えなど協力してくれる
普段、同居の兄嫁が母を介護しており、姉が通って手伝っている。自分や妹も時々行って世話をする。男のきょうだいも直接ケアはしないが、送り迎えなど協力してくれる 夫婦で暮らしている認知症の両親を姉妹3人で見ている。兄は一度同居したがうまくいかなかった経緯があり、認識のずれや気持ちのすれ違いで疎遠になっている
夫婦で暮らしている認知症の両親を姉妹3人で見ている。兄は一度同居したがうまくいかなかった経緯があり、認識のずれや気持ちのすれ違いで疎遠になっている 母を週4-5日介護している姉が心配だ。姉は母が死んだら燃え尽きてしまうかもしれない。姉も友人から介護生活だけでなく社会とのつながりを持つように言われたと話していた
母を週4-5日介護している姉が心配だ。姉は母が死んだら燃え尽きてしまうかもしれない。姉も友人から介護生活だけでなく社会とのつながりを持つように言われたと話していた 小学校高学年の頃父母と川の字になって寝ていた時に、病弱だった父が母に俺が死んだらどうする?と言っているのを聞いた。子ども心に母の面倒は自分が見るという使命感を抱いた
小学校高学年の頃父母と川の字になって寝ていた時に、病弱だった父が母に俺が死んだらどうする?と言っているのを聞いた。子ども心に母の面倒は自分が見るという使命感を抱いた 親子3人でタッグを組んで頑張ろうと認知症の両親の介護にのめり込んだ。夫や子どもたちは両親の変化を自然に受けとめ、きりきりしていた私とバランスが取れていたと思う
親子3人でタッグを組んで頑張ろうと認知症の両親の介護にのめり込んだ。夫や子どもたちは両親の変化を自然に受けとめ、きりきりしていた私とバランスが取れていたと思う 娘と介護を分担するつもりはないが、姑が呼んでいると教えてくれたり、姑におばあちゃんと声をかけたり、お母さん大変ねと気遣ってくれたりする娘の存在に助けられた
娘と介護を分担するつもりはないが、姑が呼んでいると教えてくれたり、姑におばあちゃんと声をかけたり、お母さん大変ねと気遣ってくれたりする娘の存在に助けられた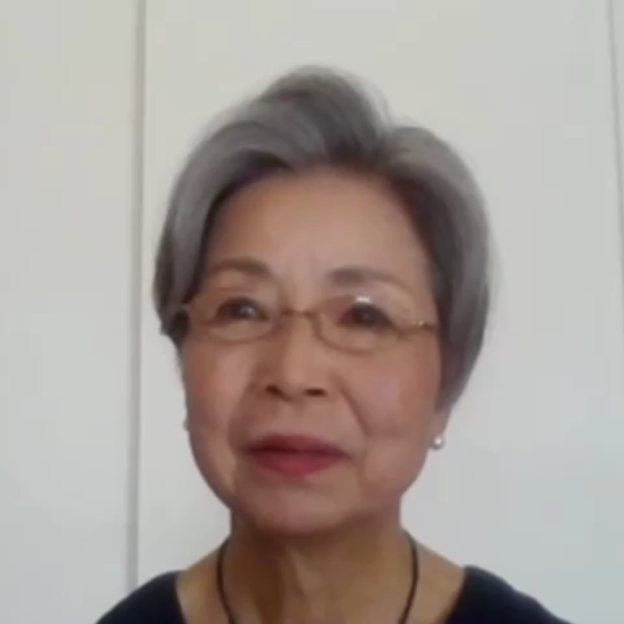 子供がまだ小さく勤めに出ずにいた娘に「家での待機も仕事の内だから、お母さんのお給料を半分受け取って」と懇願し、介護に協力してもらった
子供がまだ小さく勤めに出ずにいた娘に「家での待機も仕事の内だから、お母さんのお給料を半分受け取って」と懇願し、介護に協力してもらった 妻の介護と仕事の両立は、仕事を辞めて協力してくれた義母の助けなしに成り立たなかった。高齢の義母は、最近では持病が悪化し、もう体力的に無理な状況だと話している
妻の介護と仕事の両立は、仕事を辞めて協力してくれた義母の助けなしに成り立たなかった。高齢の義母は、最近では持病が悪化し、もう体力的に無理な状況だと話している 施設に入っていた妻を引き取り介護している。できれば、ゆくゆくは息子たちの誰かにこの家に来てもらい、世話になりたいが、その話になると喧嘩になってしまう
施設に入っていた妻を引き取り介護している。できれば、ゆくゆくは息子たちの誰かにこの家に来てもらい、世話になりたいが、その話になると喧嘩になってしまう 病院では先生が丁寧に説明してくれるからありがたいが、専門的なことはわからないので、離れに同居している息子夫婦が一緒に行ってくれる
病院では先生が丁寧に説明してくれるからありがたいが、専門的なことはわからないので、離れに同居している息子夫婦が一緒に行ってくれる